作家在廊:6(土)
会期中無休

väv(ヴェーヴ)はスウェーデン語で「織る」の意味。今年はカシミヤの単糸を使い、より薄く・軽やかに仕上げた正方形のスカーフサイズを織っていただいた。とにかくこのサイズは便利。室内でもシルクスカーフのようにクルクルっと巻く。ハンカチのようにクシャクシャっとポケットに仕舞う。もっと寒い時は、大判のストールと重ね付けしても良いだろう。凍てつく冬のなか、太陽の光のように明るく射す色を織る。スウェーデンで染織物を学んだ大滝さんならではの大胆な色の取り合せ、複雑な図案が目を惹く。
イエローを基調として、さまざまなラインが走るスカーフには35のパターンが織り込まれている。もともとサンプルとしてリネンで意図せず織られた、素材の欠片だったが、私にはキラキラと魅力的に映った。既にそこに存在する、ありのままを風景にしてもらい、結果的には細やかなテクニックを盛り込んだ、贅沢な1枚となった。
相変わらず、ほとんどの糸を自身で染めている。例えばイエローという色にもグラデーションがあり、この場合は青みを感じるレモンのようなイエローだ。小さいが、スカーフの顔をしたテキスタイル-väv-の醍醐味を大いに感じる。それは色、手触り、温もりといった感覚的に好きな要素と要素をギュッと建築学的に詰め合わせにした、とてもハッピーなセットなのだ。
略歴)
大滝郁美(Ikumi OTAKI)
山形県出身。スウェーデン、ダーラナ地方にある手工芸学校で3年間、現地の文化や自然の中で大切に受け継がれてきた、伝統的な織物や手工芸を学ぶ。
https://itori-vav.com
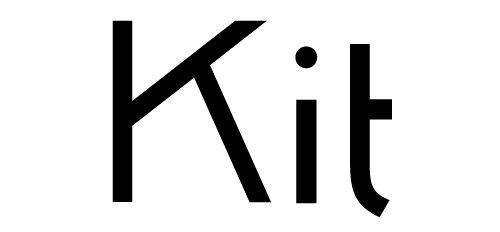



























 この立ち上がりがギリギリだというプレート
この立ち上がりがギリギリだというプレート 成形している間にも崩れやすい、ゆるゆるの土
成形している間にも崩れやすい、ゆるゆるの土 失敗した作品が鋳型になる
失敗した作品が鋳型になる

 「底が可愛くなった♡」と喜ぶ壷田さん
「底が可愛くなった♡」と喜ぶ壷田さん


